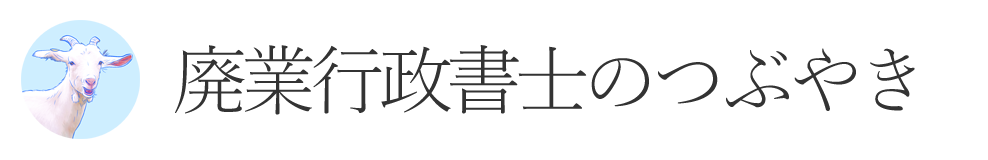私は現在、3箇所のお墓を守っています。
1つ目は両親が眠っている墓、2つ目は父の故郷の墓、3つ目は妻の父が亡くなった時に建てた墓です。
その1つ目の墓は、私が死んだらほぼ間違いなく入る墓です。その2つ目は、父の兄夫婦に子どもがいなくて、義理の伯母の遺言により墓守と供養を託された、父の系統の先祖代々墓です。300キロ近く離れた新潟にあるので、そうそうには行けず、年に1回、その菩提寺へ伺って、お経をあげてもらい、お布施と護持会費(墓地管理費)を納めております。その3つ目は、いまは妻の父が眠っています。そして、97歳になる義母がそう遠くない将来にここで永眠することでしょう。
私の代では、しっかり墓守していきます。ですが、私や妻の死後、あるいは重い認知症にでも罹ってしまった場合、墓守・供養してくれる者がいるかと思案したとき、何やら悲観的になってしまう自分がいます。
36歳になるわが愚息、仕事は一応まじめにやっているようですが、独身のまま、おそらく結婚はしないでしょう。彼女どころか友だちもいない様子ですし、とにかく、偏屈なのです。そう育てた親が悪いといわれれば返す言葉はありませんが、不登校とか引きこもりになりませんでした。この点は、ほんとありがたかった。ただ、人付き合いが悪いタイプなのです。
私には二人の姉がいますが、それぞれの子どもたちには子(=姉たちにとっては孫)がいません。なので同じように墓守がいなくなる可能性が大です。
墓苑に管理費を支払いませんと、やがては、合祀とか共同墓へ移されてしまいます。現に、母の兄夫婦(私の伯父・義伯母)の場合もお子さんがいなくて、すべてを相続した義伯母の兄が死んだあと、その子供たちによって、その墓苑の一角にある共同墓へ移されてしまいました。
聞くところによれば、田舎の先祖代々の墓では、荒れ放題、草ぼうぼうとなってしまったものが増加の一途なのだとか。そもそもお寺でさえ、後継者がいなくて廃止届を出すところが増えてきたとか。いうことを聞かない子供を「寺の小僧に出すぞ」と言って恫喝するシーンが昔はいたるところであったようですが、それも今は昔、寺にそんな余裕はなくなっています。